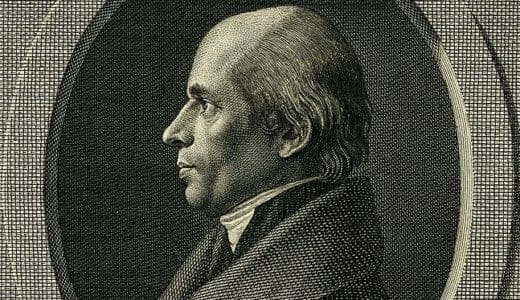記憶術には2500年の歴史がある
記憶術の歴史は古く、なんと2500年の歴史があります。紀元前500年頃の古代ギリシアで誕生して以来、記憶術は、哲学者、弁論者、修道士、大学教授、知識人といった知識人達によって考案され発展し、使われてきた歴史があります。
しかも紀元前6世紀の古代ギリシアで考案された記憶術(座の方法)は、今もなお使われていて、座の方法から派生した記憶術は30種類を越えるようになっています。⇒記憶術の一覧
欧米では、記憶術は真っ当な記憶の技術として評価され、現代においても多くの人が習得に励んでいます。
ところが日本では、明治時代にいかがわしい形で導入され、誇大広告も相まって、記憶術への評価が低く、現在でも胡散臭い・嘘・詐欺・騙していると思われている節があります。
日本における記憶術の扱いは低いため、その真価はほとんど理解されていません。けれども現在は、日本でも多くの記憶術本が出版され、記憶術への理解も広まってきています。
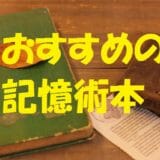 【2026年】記憶術の本おすすめ8冊書籍ランキング
【2026年】記憶術の本おすすめ8冊書籍ランキング
記憶術の歴史で大事な5つの出来事
記憶術の歴史には、大きく分けて5つのエポック(画期的な)出来事があります。それは、
- 「座の方法(場所法、記憶の宮殿)」の発明・・・紀元前6世紀のシモニデス
- 「想像上の記憶の宮殿」の発明・・・中世(11~15世紀)のスコラ哲学の時代
- 「変換記憶術」の発明・・・17世紀のウィンケルマンとリチャード・グレー
- 記憶術のビジネス化・・・19世紀のグレガー・ファイネーグ
- 「オンライン型記憶術」の登場・・・21世紀に登場した記憶術の習得が容易な「オンライン」記憶術学習システム
といった5つの出来事と歴史です。記憶術の歴史を理解する際には、これら5つの出来事を踏まえると記憶術の歴史を俯瞰してとらえることができるようになります。
記憶術は2500年の歴史を誇る「記憶の技術」であって、人為的な努力によって記憶力を確実に伸ばすことができる優れたスキルになります。
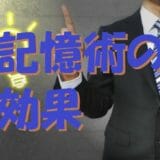 記憶術は効果がない?効果があるないの違いは何か?
記憶術は効果がない?効果があるないの違いは何か?
なお記憶術の詳細な歴史については、各ページで詳しく説明しています。このページではダイジェストで記憶術の歴史の流れをまとめています。
記憶術の発祥は古代ギリシア「シモニデス」【紀元前6世紀】
記憶術の発祥はギリシア時代になります。紀元前6世紀(紀元前500年)頃の詩人・シモニデスが記憶術を発明します。
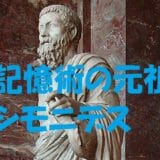 シモニデス~記憶術の起源「座の方法(ローマンルーム法)」【古代ギリシア BC500年】
シモニデス~記憶術の起源「座の方法(ローマンルーム法)」【古代ギリシア BC500年】
シモニデスは、たまたま訪問していた貴族の邸宅で地震が起きたところ大勢の人が死亡。ところが人々が座っていた場所を覚えていたため、遺体が誰であるのかがわかったといいます。
この出来事からシモニデスは、「座っていた場所(座)」と「覚えたい対象」を関連付けて記憶する「座の方法(ローマン・ルーム法)」を考案します。
これが記憶術の始まりになります。で、シモノデスが考案した記憶術こそ、現代でも記憶術の最高峰といわれている「場所法」になります。
 記憶術・場所法とは?メリットもデメリットも完全解説!
記憶術・場所法とは?メリットもデメリットも完全解説!
なお同じ頃、ギリシアではメトロドロスは占星術を使った記憶術を考案しています。
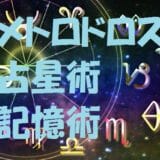 哲学者メトロドロスが記憶術を完成~占星術的記憶術【BC300年】
哲学者メトロドロスが記憶術を完成~占星術的記憶術【BC300年】
記憶術を広めた古代ローマの政治家「キケロ」【紀元前2世紀】
その後400年くらいしてからの紀元前2世紀(紀元前100年)頃、古代ローマでは政治家キケロが現れて、シモニデスの記憶術を広めます。
 政治家キケロの記憶術【ローマ時代 BC100年頃】
政治家キケロの記憶術【ローマ時代 BC100年頃】
キケロが活躍したローマ時代では、記憶術は弁論術に使われます。「ヘレンニウスへ」「弁論家について」「弁論術教程」の三冊は記憶術の三大古典書となりますが、この頃に著されています。
 記憶術における三大古典【紀元前後ローマ時代】
記憶術における三大古典【紀元前後ローマ時代】
古代ローマ時代では、記憶術は弁論に使われていましたが、これは現代で言うところのスピーチやプレゼンテーションに相当します。記憶術は現代でも有効なことは、歴史を振り返るとよくわかります。
記憶術がキリスト教で使用【11~15世紀】
その後しばらくの間、記憶術の歴史は特に進展はありませんが、11世紀頃からキリスト教の教会や修道院の教育機関(現在の大学)において、神学や倫理を覚えるために記憶術が積極的に使用されます。
またキリスト教神学を哲学化したスコラ哲学では、煩瑣な知識を覚える際に、記憶術が使われるようになります。
スコラ哲学の「架空の記憶の宮殿」
ちなみにスコラ哲学で使用した記憶術は、シモニデスの記憶術(実在する座:記憶の宮殿)は使いませんでした。
その代わりに、キリスト教の宗教的概念を「記憶の宮殿」に使う独特のやり方を採用。言い換えれば「想像上の記憶の宮殿」を使ったやり方でした。
概念を記憶の宮殿に使うやり方は、この時代特有の記憶術の使い方になります。記憶術の使い方としては革命的だったりします。
 記憶術がスコラ哲学・学問に使われた中世【11~15世紀】
記憶術がスコラ哲学・学問に使われた中世【11~15世紀】
修道士・聖人が記憶術を考案&使用
またこの当時、修道士が記憶術の方法を考案します。たとえば修道士のポンコンパーニョ、トマス・アクィナスがいます。トマス・アクィナスは列聖ともなった聖人(聖者)です。
現代では信じがたいかもしれませんが、当時は聖人(聖者)が記憶術を使い、考案していました。なおトマス・アクィナスの記憶術は、ペトラルカ、ラゴーネといった修道士達に受け継がれていきます。
このように中世においては、記憶術は大学(アカデミック)で使われます。教会の権威でもあるドミニコ会の修道士らは、記憶術は「知識を覚えるための重要な手段」としていました。
このように歴史を鑑みると、記憶術は知識人の代表だった修道士や聖者が考案し使用を推奨していたことは注目に値します。記憶術が真っ当な記憶の技術であることを端的に示していることもわかります。
記憶術がオカルト・ビジネス・学問で使用されたルネサンス期【15~16世紀】
やがてルネサンスの時代を迎えます。ルネサンス期の15世紀後半に印刷技術が登場します。
印刷技術の登場によって聖書が普及するようになります。そうなると修道士の間で一子相伝のように継承されてきたキリスト教神学や倫理道徳の教えの暗記を、わざわざ行う必要がなくなっていきまかした。
印刷技術が普及するにつれて、印刷された聖書を読むようになります。そうして修道士の間では記憶術の使用が減っていきます。
 ルネサンス期の記憶術~神学・オカルト・ビジネスに使用【15~16世紀】
ルネサンス期の記憶術~神学・オカルト・ビジネスに使用【15~16世紀】
オカルトに記憶術を使用
ルネサンス期においてキリスト教神学や倫理道徳を記憶術で覚えることが廃れた一方、記憶術は新プラトン主義、ヘルメス主義、カバラといいた神秘学やオカルトの世界で使用されます。ちなみにこれらは、
- 新プラトン主義・・・宇宙の根源と一体になること(ワンネス)、インドでいう梵我一如
- ヘルメス主義・・・オカルト全般(魔術、占星術、錬金術など)
- カバラ・・・ユダヤ教のオカルト(秘教、神秘学)
このような意味になります。
ちなみに当時の代表的な記憶術家には「ドミニコ会修道士」であり、たとえば、ラモン・ルル、ジュリオ・カミッロ、ジョルダーノ・ブルーノ、ロバート・フラッドといった修道士がいます。
 ラモン・ルルの記憶術はマインドマップのルーツ【13世紀】
ラモン・ルルの記憶術はマインドマップのルーツ【13世紀】  ジュリオ・カミッロの「記憶の劇場」オカルト・魔術的な記憶術【16世紀】
ジュリオ・カミッロの「記憶の劇場」オカルト・魔術的な記憶術【16世紀】  ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】
ジョルダーノ・ブルーノの記憶術「イデアの影について」【16世紀】
ビジネスに記憶術を初めて使用
ルネサンス期には、記憶術を世俗的に使用する萌芽も見られます。また記憶術をビジネスに利用することが、15世紀の終わりから登場します。
記憶術をビジネスに利用した元祖はラヴェンナのペトゥルスになります。彼は記憶術を「人生における成功術」として初めて活用した人でもあります。
またペトゥルスは世界で初めて記憶術本を出版もしています。
 世界初の記憶術本~ラヴェンナのペトゥルス「不死鳥」【15世紀】
世界初の記憶術本~ラヴェンナのペトゥルス「不死鳥」【15世紀】
記憶術をビジネスに使用する傾向は、19世紀になると顕著になりますが、先駆けはルネサンス期にあったということになります。
学問に記憶術を使用
ルネサンス期には、古典記憶術とスコラ哲学記憶術を包括した新しい記憶術も登場します。
つまり、シモニデス系の「座の方法」と、スコラ哲学系の「概念を記憶の宮殿(メモリーパレス)」の2つの系統の記憶術を折衷した記憶術です。
「記憶の宮殿」が作りやすい記憶術ともいえます。この方法は、修道士のロンベルヒや、哲学者のフランシス・ベーコン、デカルトも使っていました。
また哲学者であり数学者であったライプニッツもこの記憶術を使用していました。
 ヨハンネス・ロンベルヒ「記憶術集成」~音・形を使った変換記憶術【16世紀】
ヨハンネス・ロンベルヒ「記憶術集成」~音・形を使った変換記憶術【16世紀】  フランシス・ベーコンとルネ・デカルトの記憶術~学問で使う【16世紀】
フランシス・ベーコンとルネ・デカルトの記憶術~学問で使う【16世紀】
変換記憶術の発明【17~18世紀】
ルネサンス期が終わって17世紀に入ると、画期的な記憶術が登場します。それは「変換記憶術」です。「変換記憶術」とは、数字や抽象的な言葉を覚えるための記憶術です。
一般的に数字や抽象的な言葉は覚えにくいものです。ところが17世紀から18世紀にかけて、覚えにくい難しい言葉や数字を簡単に覚えるためのの記憶術が発明されます。
変換記憶術を考案した代表的な2人がいます。それは、
の2人です。2人は変換記憶術を考案して、記憶術を飛躍的に使いやすい記憶のテクニックとしています。
ちなみに現在でも使用されている「ペグ法」も変換記憶術で、これを考案したのはウィンケルマンになります。
 ウィンケルマン【ドイツ】は数字を覚える記憶術を発明【17世紀】
ウィンケルマン【ドイツ】は数字を覚える記憶術を発明【17世紀】  リチャード・グレー【イギリス】文字変換法記憶術の創始者【18世紀】
リチャード・グレー【イギリス】文字変換法記憶術の創始者【18世紀】
なお「ウィンケルマン」は作家で歴史家だった知識人。「リチャード・グレー」はオックスフォード大学を卒業した英国国教会の牧師でした。記憶術は知識人(インテリ)が考案し使用するといった歴史は、紀元前500年から脈々と受け継がれていることがわかります。
記憶術の大衆化【18世紀】
また18世紀には、記憶術の大衆化が起こります。それまでは弁論、学問、宗教、オカルトといった分野で使われていた記憶術でしたが、この頃より大衆に広まっていくようになります。
記憶術の大衆化で顕著なのは、「人生に成功するための記憶術」として広まっていった点です。
記憶術を成功術として使用することを考案したのは、15世紀のペトゥルスが元祖になります。が、ペトゥルスのアイディアは17世紀になると世間に広まっていくようになります。
記憶術ビジネスの元祖ファイネーグ【19世紀】
19世紀に入ると欧米では記憶術が流行。記憶術はビジネス化し商売の道具として使用されるようになります。記憶術のビジネス化は19世紀から盛んになり、欧米では一大ブームになります。
ルネサンスが終わった17世紀になり、変換記憶術を発明したウィンケルマン、リチャード・グレーが登場して以来、記憶術の専門家は欧米で増えていきます。
こうした中、記憶術をビジネス化する動きも出てきますが、この先駆けとなったのが、19世紀のグレガー・ファイネーグ。
ファイネーグはローマカトリック教会の修道士でしたが、記憶術の専門家にもなって、記憶術をお金儲けの手段として使い始めます。
記憶術を統合したファイネーグ
グレガー・ファイネーグは、シモニデスの「座の方法(場所法)」やスコラ哲学的な記憶術(想像の記憶の宮殿を使う場所法)、またウィンケルマンやリチャード・グレーが発明した「変換記憶術」をまとめあげて「記憶術大全」とします。
で、これを元にしてファイネーグは「記憶術のビジネス化」を始めます。別の言い方をすれば、記憶術を総まとめをして商品として販売し始めたといえます。
ファイネーグは、現在の記憶術ビジネスの元祖ともいえます。記憶術の秘密化、高額な受講料といった特徴は、ファイネーグに由来します。
 グレガー・ファイネーグ~記憶術をビジネスにした元祖【19世紀初期】
グレガー・ファイネーグ~記憶術をビジネスにした元祖【19世紀初期】
記憶術がビジネスとなる時代【19世紀後半~20世紀】
19世紀の後半から20世紀は、記憶術はますます商品化され、ビジネスとして広まっていきます。
とはいっても大学の教授や弁護士、軍人、牧師といった知識人が記憶術の専門家となって、欧米に広めていきます。知識人(インテリ)が記憶術を担っているのはシモニデスの時代から同じということですね。
ファイネーグが始めた「記憶術のビジネス化」「記憶術テクニックの秘密化」「記憶術講座の高額化」という風潮は、この当時の特徴でもあって、これが欧米や日本にも伝播していきます。
記憶術専門家の増大
19世紀の後半から20世紀にかけての著名な記憶術専門家は、エメ・パリ、ベニウィスキィ、フランシス・フォーベル・グーロー、カール・オットー・レーベントロー、アーネスト・ウッド、ハリー・ロレインといった知識人(インテリ)らになります。
彼らが考案した記憶術は、現在でも記憶力世界選手権でも使われているほど独創性と使い勝手の良さのあるユニークな記憶術となっています。
 大学教授らの記憶術専門家の増加と欧米での流行【19世紀】
大学教授らの記憶術専門家の増加と欧米での流行【19世紀】
日本の記憶術の歴史
日本の記憶術の歴史は、
- 忍者の記憶術・・・江戸時代(17世紀)
- 井上円了の記憶術(ファイネーグの記憶術)・・・明治時代(19世紀)
- ワタナベ式記憶術・・・昭和時代(20世紀)
- オンライン記憶術・・・令和時代(21世紀)
といった具合に4つの時期に区分することができます。
忍者の記憶術【江戸時代:17世紀】
日本には、忍者が使用していたオリジナルの記憶術がありました。「忍者の記憶術」とも言えますが、江戸時代に考案されています。
「忍者の記憶術」は、実のところ高度な記憶術で、ヨーロッパでは近代になってから考案された変換記憶術が、17世紀の江戸時代には既に発明されていました。
歴史的にみれば、おそらく日本のほうがいち早く、変換記憶術を考案していたものと推察できます。
忍者の記憶術は、変換記憶術や痛みを利用した記憶術(感覚刀痕術)といった高度な記憶術だったりします。
 忍者の記憶術~不忘の術
忍者の記憶術~不忘の術
井上円了の記憶術【明治時代:19世紀】
西洋で発達した記憶術が日本に入ってくるのは、19世紀の明治時代になります。明治時代には西洋から記憶術(ファイネーグの記憶術)が輸入され、日本でも爆発的な記憶術ブームが巻き起こります。
また明治時代に、日本でも記憶術が普及し定着していくようになり、ファイネーグが始めた「記憶術のビジネス化」も日本に広まります。
井上円了が紹介したファイネーグの記憶術
日本では、ファイネーグの記憶術が1887年以降の明治20年代から大流行しします。この頃、数多くの記憶術本も出版されます。
中でも、東洋大学を創設した哲学者の井上円了は「日本の記憶術の元祖」となります。井上円了の記憶術は、ファイネーグの記憶術を翻訳したものになります。
 井上円了「記憶術講義」【明治27年】~日本の記憶術の元祖・ルーツ
井上円了「記憶術講義」【明治27年】~日本の記憶術の元祖・ルーツ
後述しますが、昭和の記憶術を代表する「ワタナベ式記憶術」は、井上円了の記憶術(ファイネーグの記憶術)の焼き直しになります。
誇大宣伝を行っていた明治の記憶術
ところで明治時代は、和田守菊次郎、島田伊兵衛といった知識人ではない民間人も、本格的な記憶術本を出版しています。
 和田守菊次郎「和田守記憶法」は東京の記憶術【明治28年】
和田守菊次郎「和田守記憶法」は東京の記憶術【明治28年】  島田伊兵衛「島田記憶術」は大阪の記憶術【明治28年】
島田伊兵衛「島田記憶術」は大阪の記憶術【明治28年】
両者ともファイネーグの記憶術であったものの、よく理解しないまま大々的な宣伝を行って、記憶術ビジネスを開始しています。
そのため、宣伝通りの効果は得られないとして、宮武骸骨から厳しい批判も受けて、記憶術が怪しく胡散臭いものとして知られるようにもなります。
欧米では、記憶術は真っ当な記憶のテクニックとして認知されています。しかし日本では嘘くさい詐欺として認知されることが多いのは、明治時代の誇大広告や宣伝による悪い評判やマイナスのイメージが根底にあるからだと考察しています。
 昔の雑誌にあった記憶術の広告とは?
昔の雑誌にあった記憶術の広告とは?
ワタナベ式記憶術の登場【昭和時代:20世紀】
昭和の時代に入ってからは、渡辺剛彰が記憶術ブームを巻き起こします。きっかけは1959年に放送したNHKテレビ「私の秘密」という番組に渡辺氏が出演したことです。
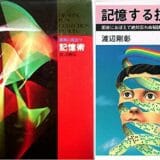 ワタナベ式記憶術【渡辺剛彰】~実際に使ったレビュー・口コミ・やり方
ワタナベ式記憶術【渡辺剛彰】~実際に使ったレビュー・口コミ・やり方
これがきっかけで日本中に記憶術なるものが知れ渡ります。
なお渡辺剛彰氏の記憶術は、父親の彰平氏から教わった記憶術が原型になっています。その彰平氏の記憶術は、井上円了の記憶術で、つまり、ワタナベ式記憶術は、ファイネーグの記憶術ということになります。
けれども渡辺剛彰の「ワタナベ式記憶術」は日本における記憶術の実質的「元祖」になります。
 東京カルチャーセンターの記憶術講座とは?口コミ・評判・レビュー
東京カルチャーセンターの記憶術講座とは?口コミ・評判・レビュー
「ワタナベ式記憶術」を皮切りに、本当に効果があって実用性のある記憶術が広まるようになります。日本の記憶術の歴史において「ワタナベ式記憶術」は画期的なことでした。
事実、ワタナベ式記憶術が登場してから、記憶術の通信講座も登場します。
 記憶術の通信講座~初心者やイメージが苦手な人向け
記憶術の通信講座~初心者やイメージが苦手な人向け
東大合格者が記憶術を普及【20世紀】
「ワタナベ式記憶術」を発表した渡辺剛彰氏は、東京大学文Ⅲ(文学部)に合格したこともあってか、昭和から平成の時代にかけては、東大合格者を中心に記憶術が発表され広まっていくようになります。
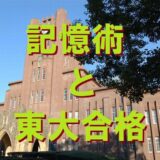 記憶術と東大合格との関係~記憶術の指導者に東大合格者は多い
記憶術と東大合格との関係~記憶術の指導者に東大合格者は多い
たとえば、宮口式記憶術、栗田式記憶術は著名で、どちらも記憶術を使って東大に合格し、その後、記憶術専門家となっています。
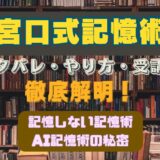 宮口式記憶術【宮口公寿】のネタバレ~実際に購入しているのでわかるその凄さ
宮口式記憶術【宮口公寿】のネタバレ~実際に購入しているのでわかるその凄さ
なお東大に合格はしていませんが、藤本憲幸氏の「藤本式記憶術」も昭和の時代に多数の著書を出しています。
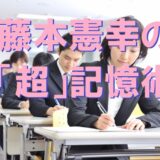 藤本憲幸の「超」記憶術とは?
藤本憲幸の「超」記憶術とは?
それにしても19世紀の記憶術をビジネス化した「ファイネーグの記憶術」は、日本では広く浸透します。日本においては、「記憶術といえばファイネーグの記憶術」といっても過言ではありません。
ユダヤ式記憶術の登場【平成時代:21世紀】
21世紀になると、記憶術だけでなく、勉強術や計画術を取り入れた新しいタイプの記憶術が登場します。
また「ユダヤ式記憶術」いった生命の樹というテンプレートを使うまったく新しい画期的な記憶術を、日本人の松平勝男氏が発明します。
 ユダヤ式記憶術とは?特徴・効果・口コミを徹底解説!【購入者によるレビュー!】
ユダヤ式記憶術とは?特徴・効果・口コミを徹底解説!【購入者によるレビュー!】
ユダヤ式記憶術は、記憶術2500年の歴史の中でも斬新なアイディアにあふれています。ユダヤ式記憶術は、ファイネーグの記憶術とは全く異なる上、西洋人も思いつかなかった記憶術になります。
それにしても「忍者の記憶術」もそうですが、日本人は独創的な記憶術を生み出している歴史もあります。
試験合格に特化した記憶術が多く登場【21世紀】
なお21世紀に入ってからの記憶術は、試験合格に特化した記憶術(勉強術)が多く登場します。これは記憶術が学校受験や資格試験の合格のために使われるといったことと関係していると思われます。
が、この現象は1950年以降のベビーラッシュとも関係があり、子どもの人数が多いと学校受験や資格試験の勉強に励むマーケットが大きくなるため、これと連動して記憶術も試験合格に特化されるようになっていったものと思われます。
ちなみに記憶術の利用者が多くなるにつれ、記憶術の習得を容易にしようとする工夫もみられてくるようになります。
科学的な記憶法の登場【令和時代:21世紀】
さらに令和の時代になってからは、東大理Ⅲに合格した河野玄斗氏、メンタリスト DaiGo氏らが登場します。シモニデスなどの従来の記憶術に加えて、科学的な方法による「記憶法」を取り入れている点に特徴があります。
 河野玄斗の驚異的な暗記法は場所法・語呂合わせ記憶術だった
河野玄斗の驚異的な暗記法は場所法・語呂合わせ記憶術だった  メンタリストDaiGoおすすめの【記憶の宮殿】は記憶力を高める方法だった!
メンタリストDaiGoおすすめの【記憶の宮殿】は記憶力を高める方法だった!
人間の生理的な仕組みを生かした「記憶法」とともに「記憶術」を使っている点は、まさに「科学的」です。
オンライン記憶術講座の登場【令和時代:21世紀】
また令和の時代になると、インターネットの利点をフル活用し、それまでは実現不可能だった「マンツーマン形式」の指導と、手厚いサポートを実現した「オンライン記憶術講座」が登場します。
たとえば、大野元郎「大野式記憶術」、吉野邦昭「吉野式記憶術」、宮地真一「宮地式脳トレ記憶術」、吉永賢一「吉永式記憶術」といったオンライン型の記憶術講座があります。
 大野式記憶術(記憶の学校)とは?【口コミ、ネタバレ、やり方】
大野式記憶術(記憶の学校)とは?【口コミ、ネタバレ、やり方】  吉野式記憶術2.0【吉野邦昭】とは?やり方・口コミ・金額・ネタバレ~人生を成功に導く記憶術
吉野式記憶術2.0【吉野邦昭】とは?やり方・口コミ・金額・ネタバレ~人生を成功に導く記憶術  “宮地式脳トレ記憶術”を徹底解明~やり方・ネタバレ・レビュー・値段
“宮地式脳トレ記憶術”を徹底解明~やり方・ネタバレ・レビュー・値段 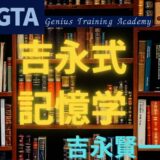 吉永式記憶術(吉永式記憶学)を徹底解明!~やり方・ネタバレ・受講料・LINE登録などをレビュー
吉永式記憶術(吉永式記憶学)を徹底解明!~やり方・ネタバレ・受講料・LINE登録などをレビュー
これらのオンライン記憶術講座は、親切・丁寧な指導とサポートが特徴で、インターネットの利便性をフルに活用し、「誰でも記憶術が習得できる」ことを実現しています。
誰でも記憶術を学び使える時代【21世紀】
昔は「頭が良い」「理解力がある」「文字が読める」といった知識人(インテリ)のみに使われていた記憶術だったものです。そのため、政治家(弁論家)、哲学者、修道士、大学教授といった知識人が考案し使用することが多かったものです。
しかし19世紀になってから記憶術が大衆化し、さらに21世紀になると、「誰でも記憶術を身につけることができる」「誰でも記憶術が使えるようにする」といった点にフォーカスされ、記憶術が再び新しい局面を迎えるようになっています。
また令和時代の記憶術(オンライン記憶術)の特徴として、記憶術から胡散臭さが無くなり、表現がやさしくかつ親身になり、また大衆化とともにインターネットを使った講座が開催され、ハイレベルな記憶術がより簡単に習得できるようになってきたというのがあります。
令和になってからは、記憶術が能力開発や優れた自己投資として認識され、新しい様相を見せ始めています。
ちなみに記憶術には相性もあります。自分にあった記憶術を使うことから始めるのがおすすめになります。
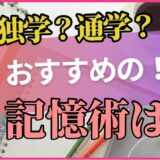 あなたに合ったおすすめの記憶術~これならできる!
あなたに合ったおすすめの記憶術~これならできる!
記憶術は知識人による歴史
以上が記憶術の歴史になります。記憶術の歴史を鳥瞰するとおわかりかと思いますが、記憶術は元々知識人(インテリ)が扱う「記憶の技術」でした。
日本では怪しいものと思われている節がまだありますが、理解力の乏しい大衆の手にかかると、胡散臭いものとして受け止められてしまうこともあると思います。
けれども記憶術は、真っ当な記憶のスキルであって、このことは2500年の記憶術の歴史をみればわかることですね。
記憶術は進化し続けている
そんな記憶術は「秘密技術」としての側面があります。しかし記憶術の原理原則はほぼ公開されています。が、記憶術を簡単に習得する秘訣や、自在に使いこなす工夫は、記憶術専門家が自家薬籠中の物のように秘密にして扱っています。
現代の記憶術においても、使い方やノウハウに秘密があったりして、こうしたものがマニュアルになって販売されていたり、講座やセミナーで教えられています。
しかし令和の時代になってからは、「記憶術のハード(原理やテクニック)」から「記憶術のソフト(記憶術を誰もが習得ができる)」という面にフォーカスされてきています。今や「記憶術をいかにわかりやすく教えることができるのか」がテーマにもなってきています。
中世の時代にはアカデミックに使われた記憶術は、今後、優れた自己投資や能力開発の技術として注目もされることでしょう。そうして記憶術の真価を発揮するようになり、記憶術はこれからも進化し続けていきますね。
★現代記憶術でもっともおすすめな記憶術2つ
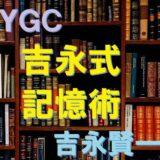 吉永式記憶術とは?究極の記憶術「イメージ連結法」を教える資格試験にも強い記憶術
吉永式記憶術とは?究極の記憶術「イメージ連結法」を教える資格試験にも強い記憶術  ユダヤ式記憶術は全く新しい記憶術!~リアル購入者による徹底解説【レビュー・ネタバレ】ユダヤ式の理解を助ける特典付き!
ユダヤ式記憶術は全く新しい記憶術!~リアル購入者による徹底解説【レビュー・ネタバレ】ユダヤ式の理解を助ける特典付き!