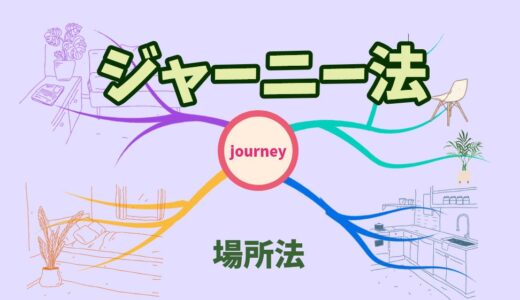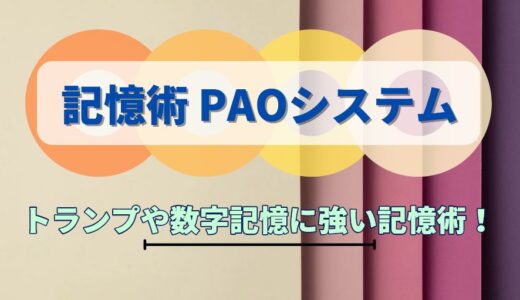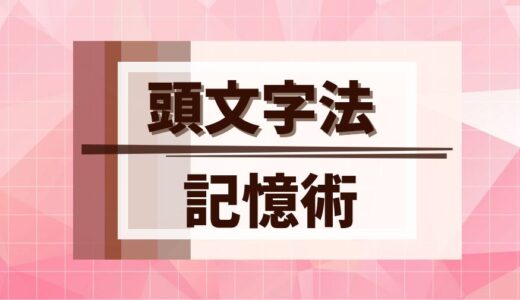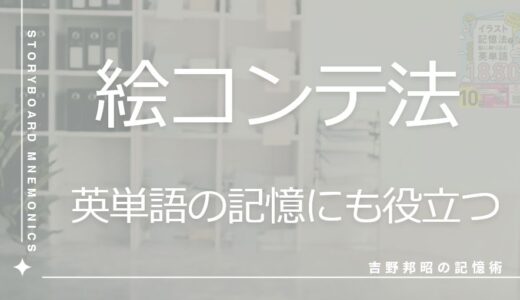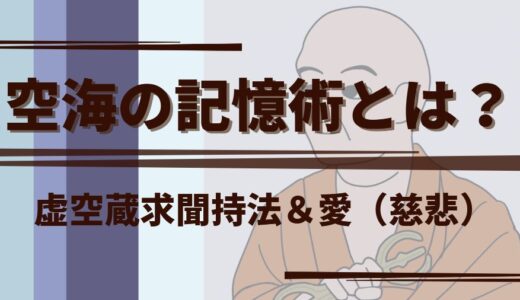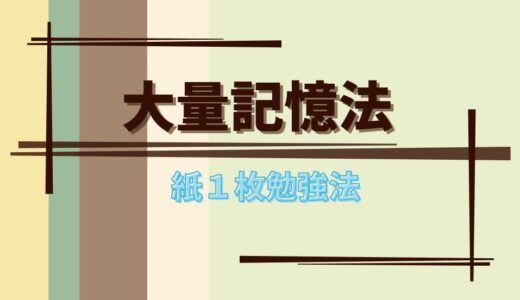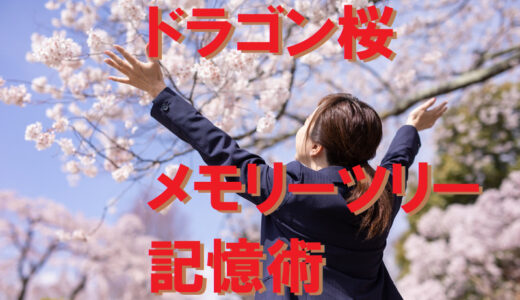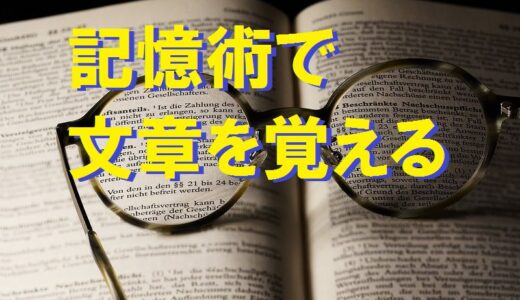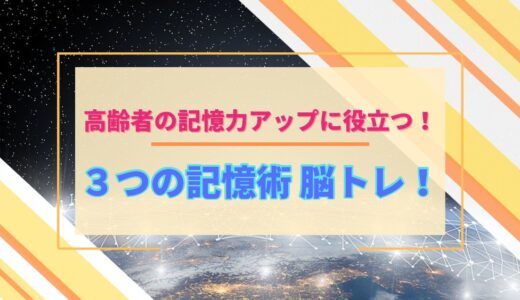記憶術は3種類&33の方法に分類できる
記憶術には種類があります。記憶術は3種類・33の方法(テクニック)に大別できます。で、記憶術を大きく分けると3種類(3つのタイプ)に分けることができます。それは、
- イメージ型記憶術・・・19種/イメージを使った記憶術
- イメージ型変換記憶術・・・8種/イメージを使った変換のための記憶術
- 非イメージ型記憶術・・・6種/イメージを使わない記憶術
これら3種類です。
世の中にある記憶術のすべては、これら3種類に区分できて、33種類のテクニックに集約することができます。新しく登場する記憶術であっても、これらの亜流か組み合わせになります。
以下、それぞれについてご説明いたします。
イメージ型記憶術は19種類
記憶術の中で最も多いのが「イメージ型記憶術」です。記憶術の中でも80%以上を占めています。
イメージ型記憶術は「頭の中にイメージを描いて覚える」やり方になります。ほとんどの記憶術が「イメージ型記憶術」になります。
イメージ型記憶術は、3つの基本技術から成り立っています。それは、
・連想力
・連結力
・変換力
です。イメージ型記憶術は、この3つを組み合わせた記憶術になっています。
 連想力【イメージ記憶法】~記憶術の基本
連想力【イメージ記憶法】~記憶術の基本  連結力【関連付け記憶法】~記憶術の基本
連結力【関連付け記憶法】~記憶術の基本  変換力【記憶術の基本】~文章・数字・専門用語・概念を覚える
変換力【記憶術の基本】~文章・数字・専門用語・概念を覚える
これらの基本スキルは、通信講座、オンライン講座、あるいは著書や教材、ネット情報で学ぶことができます。
なお2023年に登場した吉永賢一氏の「吉永式記憶術術」は、誰でもしっかりとしたイメージができる「イメージ連結法」を教え、あらゆる記憶術が使えるようにもなっています。多くの人に記憶術の門戸を開いた画期的な記憶術も最近では登場しています。
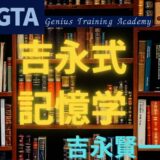 吉永式記憶学【GTA】 進化した吉永式記憶術のやり方・ネタバレ・受講料・LINE登録などレビュー
吉永式記憶学【GTA】 進化した吉永式記憶術のやり方・ネタバレ・受講料・LINE登録などレビュー
イメージ型記憶術の一覧(19種類)
イメージ型記憶術「通常の記憶術」・・・イメージを使った記憶術。通常の記憶術。
- 基礎結合法(リンク法)
- 連想結合法(リンク法)
- イメージ連結法(吉永式記憶術)
- 場所法
- 記憶の宮殿
- 身体法
- 指法
- 時計法
- 建物法
- 部屋法
- 道法
- 鈴なり式記憶術
- マインドマップ記憶術
- メモリーツリー記憶術
- ドラゴン桜記憶術
- 物語法(ストーリー法:イメージ型)
- 絵コンテ法
- ペグ法
- PAOシステム
以下、19種類の「イメージ型記憶術」について解説していきます。
1.基礎結合法(リンク法)
「基礎結合法」はイメージ型記憶術の基本中の基本のテクニックになります。「リンク法」ともいいます。
「基礎結合法」は、記憶術で要となる「イメージの仕方」をシンプルに使った記憶術になります。原理的には場所法と同じになりますが、「基礎結合法」はもっとシンプルなやり方になっています。
「基礎結合法」を知らずしてイメージ型記憶術を語ることはできないほど超重要かつ超基本的な記憶術になります。
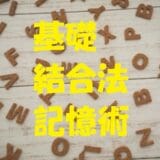 基礎結合法記憶術~一番大事な基本テクニック
基礎結合法記憶術~一番大事な基本テクニック
2.連想結合法(リンク法)
「連想結合法」も基本スキルになる記憶術です。これも「リンク法」ともいいます。
「基礎結合法」が基盤にあり、基礎結合法を発展させた記憶術が「連想結合法」ともいえます。「連想結合法」から「物語法(ストーリー法)」が誕生しているくらいです。
連想結合法は、イメージで数珠つなぎに覚え続けていくテクニックになります。記憶術においては、基礎結合法と並ぶ重要な基礎スキルになります。
 連想結合法記憶術~イメージで結合する基本テクニック
連想結合法記憶術~イメージで結合する基本テクニック
3.イメージ連結法(吉永式記憶術)
「イメージ連結法」は、吉永賢一さんが考案した記憶術(吉永式記憶術)です。原理としては「リンク法(基礎結合法、連想結合法)」と同じですが、イメージの仕方に改良が加えられています。
「イメージ連結法」は、記憶術で最も重要となる「イメージの仕方」を確実かつしっかりとできるように「4つの記憶テクニック(つなげる、またやる、小技、変換)」があります。イメージ連結法は、「あらゆる記憶術の基礎」となりつつも「あらゆる記憶術を使いこなせる」記憶術です。
記憶術を学ぶ場合は、まず「イメージ連結法」から習得したほうが良いとさせ言える重要な記憶術となっています。
4.場所法
「場所法」は記憶術の中ではもっとも古く最も優れた古典的な記憶術になります。場所法は記憶術の代名詞になっているほどです。場所法は、座の方法、ローマンルーム法、ロキ・システム、記憶の宮殿、ジャーニー法などとも言われています。記憶術を代表するやり方です。
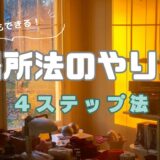 場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法!
場所法のやり方~誰でもできる4ステップ方法! 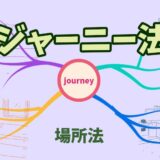 ジャーニー法(旅法)記憶術とは?~メモリースポーツでは必須の記憶術
ジャーニー法(旅法)記憶術とは?~メモリースポーツでは必須の記憶術
場所法は、リアルに存在する場所や架空の場所を用意して(これを「記憶の宮殿」といいます)、ここへ記憶したいことをイメージで関連付けて覚えていく方法になります。連想式・写真式ともいいます。
しかし場所法にも欠点があります。それは「記憶の宮殿」に多くの情報を詰めすぎてしまうと混乱してしまい覚えること自体に混乱が出てくることです。
また暗記する際に「記憶の宮殿」を整とんしておかないと、せっかく覚えた知識を引き出すことができなくなることがあります。
場所法は最も効果の高いイメージ型記憶術になりますが、事前の準備が必要な方法でもあります。場所法の使い方が下手であると、うまく覚えることができないといったデメリットも出てきます。
 場所法の7つの欠点・問題とその改善方法
場所法の7つの欠点・問題とその改善方法
なお場所法には亜流のやり方も多くあります。
場所法は工夫をすることで使い勝手のよい記憶術になります。現在出回っている有料の教材の多くは場所法を使い、工夫をほどこし、応用の効いた優れた記憶術になっています。
場所法は記憶術の王者でもあって、資格試験や大学受験の勉強に活用することができます。まさに最強の記憶術になります。
5.記憶の宮殿
「記憶の宮殿」とは場所法で使用する「記憶の座」をいいます。場所法における要こそ「記憶の宮殿」になります。
しかしながら最近では「記憶の宮殿」という言葉が一人歩きして、記憶術の方法として使われることも出てきています。そこで別項目としてあげましたが「場所法」と同じことをいっています。
ちなみに「記憶の宮殿」の作り方の上手下手が場所法を使い分ける別れ目にもなっています。作り方に関しては、こちらを参考にしてください。
 記憶の宮殿の作り方~5種類の方法を解説
記憶の宮殿の作り方~5種類の方法を解説
6.身体法
身体法とは、覚えたいことを体の各所と関連づけて暗記するテクニックです。身体法は記憶術の基礎段階では必ず習得するテクニックにもなります。
たとえば、髪の毛、額、目、鼻、口といった具合に身体の各部分と、暗記すべき対象物を結びつけていくやり方です。
身体法は「ペグ法」にも似ていますが、本質は場所法になります。場所法の亜流といっていいでしょう。
7.指法
指法は、身体法の一種になりますが、指に特化して暗記する方法になります。指法は文字通り、暗記したい事項を手の指と関連づけて憶えていくやり方です。
指は10本しかありませんので大量の記憶には不向きですが、とっさに複数のことを暗記する際には大変重宝します。
日常生活やビジネスのシーンで最も使えるのが「指法」かもしれません。たとえば商談などの会話で相手が言っていることを5個くらいにポイント化して暗記できます。
商談や会議で聞いたことを後で相手に説明すると大抵、聞いた相手はびっくり仰天します。自分の頭脳が明晰であることを示すことができる日常生活では重宝する記憶術です。指法は身体法の一つにもなりますが、本質は場所法になります。
8.時計法
時計法とは、時計の文字盤(数字)を利用した基礎結合法記憶術です。本質は「場所法」になります。
時計法は文字通り、時計の文字盤に暗記した事項を関連付けて覚えるやり方です。身体の代わりに時計を使った方法ともいえます。時計法は即効的な記憶術の一つになります。
商談の際、時計法を使用すると、頭脳明晰な人物であることを相手に印象付けることもできてしまいます。なかなかスゴイ技だったりします。指法と並んで実用性はかなりあります。
9.建物法
建物法は「場所法」の一つになります。記憶の宮殿を複数の建物や部屋を利用します。
建物法は、複雑で大量の暗記をする際には役に立ちます。大学受験や資格試験では建物法を使用することが多くなるでしょう。
なお建物法では、デパートや美術館、博物館といった個性的な建物を使用するのがおすすめです。
10.部屋法
部屋法も場所法の一つです。自分の部屋、あるいは普段使用している部屋を「記憶の宮殿」として使用します。部屋法も受験や資格試験の勉強に使うことができます。
11.道法
道法も場所法の一つになります。通学や勤務に使用している道路とその両脇にある建物や看板を「記憶の宮殿」として使います。道法は、実は記憶の定着がもっとも高い場所法テクニックになります。
この記憶が高まる効果を元にして、宮口公寿氏は「宮口式記憶術」として、試験合格用記憶術として作り上げているほどです。
⇒宮口式記憶術
12.鈴なり式記憶術
「すずなり式記憶術」は、日本の記憶術の中興の祖である渡辺剛彰氏による「場所法的な記憶術」になります。
鈴なり式記憶術は、原理的には場所法と同じです。が、記憶の宮殿の使用しません。記憶の宮殿の使用しない代わりに、連想結合法で数珠つなぎにちないで覚えていきます。
実のところ、鈴なり式記憶術を活用するためには、吉永賢一氏の「イメージ連結法」のようなイメージ力が必須になります。
場所法の欠点を補っている点で鈴なり式記憶術は秀逸ですが、イメージ力が必須になる記憶術だったりします。
 鈴なり式記憶術~教科書の丸暗記に最適
鈴なり式記憶術~教科書の丸暗記に最適
13.マインドマップ記憶術
「マインドマップ記憶術」は、トニー・ブザンが考案した「マインドマップ」を記憶術に応用した使い方になります。
そもそもトニー・ブザンは記憶術愛好家です。事実、「世界記憶力選手権(WMC)」を創設したのもトニー・ブザン。1991年に創設。
しかも「マインドマップ」は、13世紀の記憶術家でもあるラモン・ルルが考案した「学問の樹」を元にしてトニー・ブザンが考案しているほどです。
 ラモン・ルルの記憶術はマインドマップのルーツ【13世紀】
ラモン・ルルの記憶術はマインドマップのルーツ【13世紀】
マインドマップは今ではビジネスでも欠かせないツールになっています。社会人も多用しています。が、元々は記憶術にルーツがあり、マインドマップ本来の使い方こそ「マインドマップ記憶術」だったりします。
 マインドマップは記憶術~使い方がわかれば記憶力アップ!【トニー・ブザン】
マインドマップは記憶術~使い方がわかれば記憶力アップ!【トニー・ブザン】
14.メモリーツリー記憶術
「メモリーツリー」とは、実は「マインドマップ記憶術」のことだったりします。
メモリーツリー記憶術は、東大請負漫画の「ドラゴン桜」の7巻62話~64話に登場しています。登場しています。
「ドラゴン桜」の影響を受けて、大学受験にマインドマップが記憶術として使われるようになり、それが「メモリーツリー記憶術」として知られ、一躍注目を浴びるようになっています。
 メモリーツリー記憶術~作り方・使い方を図解で説明
メモリーツリー記憶術~作り方・使い方を図解で説明
15.ドラゴン桜記憶術
「ドラゴン桜記憶術」とは、先述の「メモリーツリー記憶術」のことであり、また「マインドマップ記憶術」のことだったりします。
「ドラゴン桜記憶術」は、東大請負漫画の「ドラゴン桜」の7巻62話~64話には「メモリーツリー」として登場していますが、これが通俗的に「ドラゴン桜記憶術」と言われています。
 ドラゴン桜の記憶術はメモリーツリーを使った記憶法!
ドラゴン桜の記憶術はメモリーツリーを使った記憶法!
16.物語法(ストーリー法)
「物語法」は「ストーリー法」ともいいます。「イメージ」を使ったやり方と「語呂合わせ」を応用した使い方の2種類があります。
イメージ型のやり方はシンプルです。イメージをつなぎ合わせて物語りにしていくやり方です。連想結合法と本質は同じになります。しかし「物語法」は「物語(ストーリー)」を付与する点に違いがあります。
 ストーリー法(物語法)記憶術の3つのやり方と使い方
ストーリー法(物語法)記憶術の3つのやり方と使い方
17.絵コンテ法
あと「絵コンテ法」という記憶術があります。これは吉野式記憶術の吉野邦昭さんが開発したやり方です。
絵コンテ法とはユニークな記憶術で、覚えたい物事を「だじゃれ」にし、その「だじゃれ」を「絵コンテ」のようなイラストにして、イメージで覚えてくやり方です。
覚えたい物事を「だじゃれ」にしますが、大事な点は「おもしろいだじゃれ」を作る点にあります。「だじゃれ」を使って記憶を手助けするユニークなイメージ型記憶術になります。英単語の暗記では威力を発揮します。
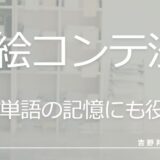 絵コンテ法 記憶術~英単語の記憶にも役立つダジヤレ式記憶術
絵コンテ法 記憶術~英単語の記憶にも役立つダジヤレ式記憶術
18.ペグ法
「ペグ法」とは、「かけくぎ法」、「フックの法」ともいいます。数字子音変換記憶術や数字仮名変換記憶術を使って数字を置き換えて、年号、電話番号、パスワードなどの数字を覚える記憶術になります。
あらかじめ「ペグテーブル」を用意しておくのがミソです。ペグテーブルにも一桁、二桁の2種類があります。
ペグ法は、身体法、指法などの記憶術と併用することも多々あります。
 ペグ法記憶術(かけくぎ法)~数字(電話番号・歴史年号)の暗記に強い
ペグ法記憶術(かけくぎ法)~数字(電話番号・歴史年号)の暗記に強い
19.PAOシステム
「PAOシステム」はペグ法をより効率よく使えるように進化させた記憶術です。メモリースポーツ(記憶力世界選手権)では、トランプを覚える際に必ず使われる記憶術です。
PAOシステムではトランプや数字を覚えるには最適な記憶術で、「人」「動き」「モノ」の3つに分けて、それぞれあらかじめ用意し、トランプや数字を覚えるやり方になります。
PAOシステムは、トランプのカードを短時間で大量に暗記するために開発されています。メモリーアスリートでは必ず使われる記憶力選手権向けの記憶術ともいえます。汎用性が乏しいといいますか、あまり一般向けの記憶術では無いと思われていますが、応用を効かせるとものすごい威力を発揮します。
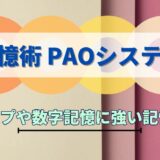 記憶術 PAOシステム~トランプカードや数字の暗記だけでなく応用が効く記憶術
記憶術 PAOシステム~トランプカードや数字の暗記だけでなく応用が効く記憶術
イメージ型変換記憶術は8種類
イメージ型記憶術の中には「変換記憶術」があります。「変換記憶術」は「イメージ型記憶術」になりますが、使い方に特徴があるため、別カテゴリーにします。
「変換記憶術」とは、覚えにくい物事や抽象的な言葉を「わかりやすいイメージにして覚えやすくする」テクニックです。変換記憶術では「変換力」が欠かせません。変換力は、変換・置換・分解・外連想といった4つのイメージ能力から成り立っています。
 変換力【記憶術の基本】~文章・数字・専門用語・概念を覚える
変換力【記憶術の基本】~文章・数字・専門用語・概念を覚える
イメージ型変換記憶術の一覧(8種類)
イメージ型変換記憶術・・・イメージを使った記憶術。「変換法記憶術」。
- 変換法記憶術
- 置換法記憶術
- 外連想法記憶術
- 分解法記憶術
- チャンク化記憶術
- 数字子音変換法
- 数字仮名変換法
- 文字変換法
以下、8種類の変換法記憶術についてご説明します。
1.変換法記憶術
「変換記憶術」は、抽象的な物事や専門用語など、馴染みの少ない言葉をいったん具体的でわかりやすい事物に置き換えるやり方をいいます。
「変換記憶術」は大変重要なテクニックになります。場所法などの記憶術を使う際に、変換記憶術を知らないと実際の使用はできないほどです。それくらい重要なスキルになります。
 変換法記憶術~変換・分解・置換・外連想の4つのテクニックからなる方法
変換法記憶術~変換・分解・置換・外連想の4つのテクニックからなる方法
2.置換法記憶術
置換法記憶術は、変換すべき物事を「あらかじめ決めておいて」、そのルールに従って変換していく記憶術になります。
たとえば、覚えたい物事を、
・五十音
・一覧表
といったように、一定のルールにしたがって変化できる下準備をしておくやり方になります。
3.外連想法記憶術
「外連想法記憶術」は、原理的には「置換法記憶術」と同じになります。
が、「置換法」と違う点は、まったく関係の無いこととやルールの無い物事と結びつけて覚えていくやり方になります。
たとえば「憲法」に対して「やかん」と連想します。突拍子もない連想になりますが、この意表を突くような連想を使って覚えていくのが「外連想法記憶術」です。
「外連想法記憶術」は、抽象的な物事を覚える際の一つのテクニックになります。
4.分解法記憶術
「分解法記憶術」は、「長い数字」や「英単語」、「文章」を、適宜分割して覚えていくテクニックになります。
分割した数字や、英単語、短文(言葉)は、語呂合わせやリンク法(イメージ連結法)で覚えていくようにします。
要するに、一度で覚えきれないものを分割して覚えていく記憶術のテクニックということになります。
5.チャンク化記憶術
「チャンク化記憶術」は、本質的には「分割法記憶術」と同じになります。しかし「チャンク化記憶術」では、分割だけでなく、分類も行い、用途の広い記憶術となっています。
「チャンク化記憶術」は、桁数の多い数字、長い英単語、文章、抽象的な概念、専門用語、文章の要点作成など幅広く使え、また思考の整理にも使うことができます。
「マインドマップ(メモリーツリー)」や「ユダヤ式記憶術」にも通じるところがある、知っておいて損は無い記憶法になります。
6.数字子音変換法記憶術
「数字子音変換法記憶術」は、数字を子音に置き換える記憶術です。変換力を使った記憶術です。17世紀にウィンケルマンが開発したテクニックです。
「数字子音置換法」は日本ではあまり使用されませんが、欧米圏つまり英語を使用する国では多用される記憶術になります。数字を覚える際、欧米圏で使う記憶術ということになります。
 ウィンケルマン【ドイツ】は数字を覚える記憶術を発明【17世紀】
ウィンケルマン【ドイツ】は数字を覚える記憶術を発明【17世紀】
7.数字仮名変換法記憶術
「数字仮名変換法記憶術」は、数字子音置換法を「日本語向け」に改良した記憶術になります。数字を日本語の仮名に置き換える方法です。
一般的に「数字変換記憶術」といっています。数字仮名置換法では、事前準備として、仮名に対応した数字を「暗記」する必要があります。
仮名と数字の対応が頭の中に作られていないと、数字仮名置換法を効果的に使用できないという面倒くささはあります。しかしいったんこの規則を憶えてしまうと、ものすごい力を発揮します。
 数字変換法記憶術~歴史年号・パスワード・生年月日など数字の暗記に最適
数字変換法記憶術~歴史年号・パスワード・生年月日など数字の暗記に最適
8.文字変換法記憶術
「文字変換法記憶術」は、イギリス人のリチャード・グレーが考案した記憶術になります。この記憶術も実のところ、日本人向けではなく、欧米人向けの記憶術になります。
「文字変換法記憶術」は、覚えやすい「言葉」を作ります。その「言葉」は、前半と後半に分かれます。
前半は覚えたいことを表す「言葉」、後半は「数字」(これをニーモニック・デバイスという)にして、造語にして覚えていくやり方が、「文字変換法記憶術」になります。
「文字変換法記憶術」はこちらで詳しく解説しています。日本人には使いにくい記憶術になりますね。
 リチャード・グレー【イギリス】文字変換法記憶術の創始者【18世紀】
リチャード・グレー【イギリス】文字変換法記憶術の創始者【18世紀】
非イメージ型記憶術は6種類
最後に「非イメージ型」記憶術です。非イメージ型記憶術の種類は少ないのですが、大変優れた記憶術もあります。
「非イメージ型記憶術」は記憶術の中でも20%以下になります。このやり方は少なかったりします。
非イメージ型記憶術は、映像やイメージを頭の中で描いて事物を覚えることはしません。言葉のリズム、音韻、語呂、ダジャレ、知識同士の関係性を使って覚えていくユニークなやり方になります。
非イメージ型記憶術は、まだまだ開発されていく可能性を秘めている記憶術であって、現代になって開発された記憶術もあります。場所法とはまた異なるものの優れた記憶術である「ユダヤ式記憶術」というのも登場しています。
非イメージ型記憶術の一覧(6種類)
非イメージ型記憶術・・・イメージを使わない記憶術。左脳型記憶術。
- 語呂合わせ
- 頭文字法
- 物語法(語呂合わせ型)
- ユダヤ式記憶術(生命の樹)
- 感覚刀痕術(忍者の記憶術)
- 論文式試験専用記憶術
以下、6種類の「イメージ型記憶術」について解説していきます。
1.語呂合わせ
「語呂合わせ」は最もよく使用される記憶術です。「語呂合わせ」を使った「歴史の年号の暗記本」は昔からいくつも出版されているほどです。
最も馴染みのある「記憶術」になります。語呂合わせを使っている科目は多く、歴史にとどまらず古文や理科でも使われています。語呂合わせはもっとも有名な記憶術といってもいいでしょう。
語呂合わせは、数字を仮名に置き換える方法が一般的です。たとえば「1」ですと「イチ、イ、ひと、ひ」などのように置き換えます。
 語呂合わせ記憶術~誰もが使える暗記方法
語呂合わせ記憶術~誰もが使える暗記方法
2.頭文字法
「頭文字法」は、文字通りで、言葉の最初の文字や音韻を並べて、そこに意味を付与することで覚えやすくする方法です。語呂合わせと同じで、昔から使われている汎用性の高い記憶術です。
ちなみに記憶術には「音韻法・形態法」というのあります。これは最初の文字や数字を取り出して、それをつなげて暗記する方法です。まさに「頭文字法」ですね。
「頭文字法」も応用の利く記憶術で、似たもの置き換えたり、記憶したい対象の頭文字を使って置き換える方法もあります。
頭文字法は、記憶術の基本テクニックである「変換力」を活かした方法にもなります。奥が深いやり方です。
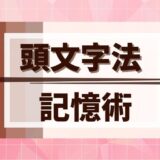 頭文字法 記憶術~スグに覚えられる記憶法の定番!
頭文字法 記憶術~スグに覚えられる記憶法の定番!
3.物語法(語呂合わせ型)
「物語法」には「語呂合わせ」を使ったやり方もあります。本来の物語法は「語呂合わせ」と「置換法(変換記憶術の一つ)」を組み合わせたテクニックになります。
語呂合わせは応用が利く方法で、たとえば物語を作っておいて、このストーリーに暗記したい事項を関連付けて覚えていくこともできます。つまり「索引・インデックス」とする使い方です。
物語法は、円周率や素数、膨大なケタの数字、あるいは文章を覚えるテクニックとしても使われています。
たかが「語呂合わせ」とあなどっていますと、こうした計り知れ合い使い方を見過ごしてしまいます。で、語呂合わせを採用しているのが「ユダヤ式記憶術」になります。
 ストーリー法(物語法)記憶術の3つのやり方と使い方
ストーリー法(物語法)記憶術の3つのやり方と使い方
4.ユダヤ式記憶術
「ユダヤ式記憶術」。おそらく初めて耳にする方もいることでしょう。しかしながら「ユダヤ式記憶術」は場所法をも上回る最強の記憶術になります。
「生命の樹」というテンプレートを使いますが、場所法の「記憶の宮殿」のように量産する必要はありません。テンプレ一つで済みます。
「ユダヤ式記憶術」は、従来の記憶術とは全くシステムが異なり、知識同士の論理などの関係性のテンプレートにはめ込んで思い出しやすくする画期的な記憶術です。
「語呂合わせ」や「物語法」との相性もよく、まさに「非イメージ型記憶術」「左脳型記憶術」の最高峰でもあって、イメージ型記憶術を苦手とする方にはぜひともおすすめしたい記憶術でもあります。
ユダヤ式記憶術は当サイトではイチオシしている優良記憶術になります。
5.感覚刀痕術(忍者の記憶術)
「感覚刀痕術」とは「感覚系記憶術」あるいは「五感型記憶術」ともいいます。渡辺剛彰氏は「感覚刀痕術」といっていました。「感覚系記憶術」はイメージを使う代わりに、聴覚、触覚、痛み、苦しみといった様々な感覚を使います。
実は昔の忍者が使っていた「不忘の術(忍者の記憶術)」を、渡辺氏は「感覚刀痕術」といっていました。「不忘の術」は感覚系記憶術ですね。
イメージに特化していませんので「非イメージ型記憶術」にカテゴライズしていますが、厳密にいえば「イメージをも包括した記憶術」ということになります。
「感覚系記憶術」はあまり知られていませんが、記憶術の本質を知り得る方法だったりします。
 忍者の記憶術~不忘の術
忍者の記憶術~不忘の術  五感を使った記憶術と「感覚刀痕術」とは?
五感を使った記憶術と「感覚刀痕術」とは?
6.論文式試験専用記憶術
また「論文式試験専用記憶術」という非イメージ型の記憶術もあります。これは小野敬人さんが考案した記憶術です。
昔からある暗記方法になりますが、工夫を凝らしていて、実用性が高くなっています。受験や資格試験において、文章を暗記する際に重宝します。
目から鱗となる意表を突いた記憶術になりますが、知っておいて損はない方法です。
3種類の記憶術の使用には適性がある
このように記憶術は大きく分けて
- イメージ型記憶術
- イメージ型変換記憶術
- 非イメージ型記憶術
の3種類に分けることができます。
で、これら3つの記憶術の使用に関しては、
- イメージ型記憶術が得意
- 非イメージ型記憶術が得意
- 両方とも使える
といった適性もあります。
記憶術の使用の際に「適性がある」ということを知りませんと、「記憶術を使っても効果が無かった」といった不平や不満が残りますので、記憶術を使う前に知っておいたほうがいいですね。
なお記憶術に適性があることは意外と知られていませんが、こちらで詳しく書いています。
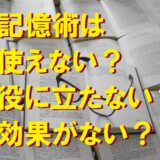 記憶術は使えないのか?~記憶術への適性チェック
記憶術は使えないのか?~記憶術への適性チェック 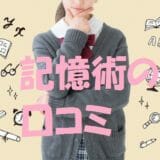 記憶術の口コミの本当と嘘~悪い口コミの7つの真実
記憶術の口コミの本当と嘘~悪い口コミの7つの真実
記憶術は記憶力を向上させる
記憶術は、記憶力を高める「術」になります。テクニックですね。
ところが、記憶術を使い続けていると、記憶力そのものが向上し、頭がよくなることがわかっています。
 記憶術で頭が良くなる?海馬が発達したメモリースポーツの脳
記憶術で頭が良くなる?海馬が発達したメモリースポーツの脳
このことは、私自身、実感しています。確かに、記憶術を使うようになってから、以前よりは記憶力が良くなっています。といいますか、正確にいえば、記憶術を使わなくても、覚えるコツが感覚にわかるようになって、物事を覚えやすくなっているということです。
このように、記憶力が良くなっています。といいますか「記憶力が良い」人は、もしかすると、こうしたことを無意識のうちに行っているのかもしれません。
それと、記憶力以外にも、判断力、処理能力、洞察力なども総じてアップしています。
このことは長年、不思議だなあと思っていましたが、上記の研究でも明らかになっていることがわかり納得したものでした。
しかも最近、このことに気がついている人がほかにもいることがわかり、その方は、吉永賢一さんですが、吉永さんは、以上のことも包括した「吉永式記憶術」を提唱されています。
「吉永式記憶術」では、記憶術によって能力そのものが高まることに注目し、独創的なやり方を採用しています。将来的に「記憶力そのもの」が良くなっていくことに興味がある方は必見だと思います。「吉永式記憶術」のことは、こちらで詳しくレビューもしています。
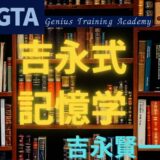 吉永式記憶学【GTA】 進化した吉永式記憶術のやり方・ネタバレ・受講料・LINE登録などレビュー
吉永式記憶学【GTA】 進化した吉永式記憶術のやり方・ネタバレ・受講料・LINE登録などレビュー
まとめ
以上のように記憶術には大別して3種類あることがおわかりかと思います。
で、記憶術を使うことができるかどうかの適性もありますので、適性チェックは必ず行っていたほうがいいですね。
なお当方のサイトより「ユダヤ式記憶術」を購入されますと、
- 代表的な記憶術の使い方とわかりやすい説明
- 記憶術の新しい使い方
- 有料講座でも指摘されていない重大なこと
- そのほか有益な情報
を記した特典が12本付いています。記憶術を受験や資格試験の勉強術に取り入れることは最適です。また記憶力の衰えを感じ始める40代・50代の方にはおすすめです。下記の記憶術講座や教材はとても役に立ちます。