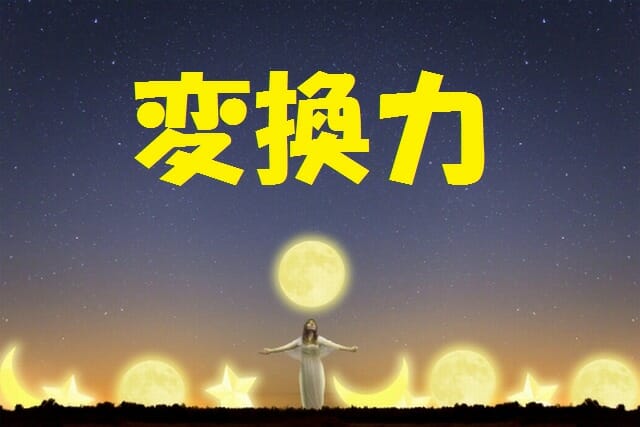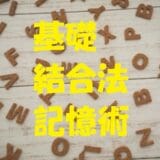※記事にはプロモーションを含む場合があります
変換力という記憶術の基本
記憶術を使いこなす基本テクニックの3番目は「変換力」になります。「変換力」は、連想力、連結力と続いて必要となる記憶術の基本技術ですね。
 連想力【イメージ記憶法】~記憶術の基本
連想力【イメージ記憶法】~記憶術の基本  連結力【関連付け記憶法】~記憶術の基本
連結力【関連付け記憶法】~記憶術の基本
この「変換力」とは「物事(暗記する対象物)を別のものに置き換える能力」をいいます。つまり「置換力」のことになります。
ところで変換力にせよ置換力にせよ、何故、これらの能力が記憶術には必要なのでしょうか。それは、文章・専門用語・数字といった抽象的なことや難解な物事の暗記に役に立つからです。
変換力は文章・専門用語・概念・数字を覚えるテクニック
そもそも物事を暗記する場合、分かりやすいものばかりとは限りませんよね?机、イス、ノートといった固有の物ばかりを覚えるとは限りません。
むしろ実際は、抽象的な概念や観念や、文章、専門用語、覚えにくい用語、あるいは数字を暗記していくことが多くなります。たとえば法律の条文や歴史の内容や年号などです。
専門用語・数字・文章の暗記は、大学受験や資格試験では多くなります。といいますかほとんどです。
記憶術の事例に登場する「いちご」「ニンジン」といった具体的かつわかりやすい物事の暗記は、実際はほとんどありません。
このような時には「専門用語・数字・文章」を「具体的で分かりやすいことに変換」していきます。あるいは「置き換え」ます。
ちなみに変換力をさらに細かくしたテクニックを「変換記憶術」といっています。
 変換法記憶術~変換・分解・置換・外連想の4つのテクニックからなる方法
変換法記憶術~変換・分解・置換・外連想の4つのテクニックからなる方法
記憶術では変換・置換能力は不可欠
この置き換えの能力が「変換力」あるいは「置換力」になります。また、変換・置き換えを素速く行う必要があります。
これらの能力はトレーニングで、スピードアップさせることができます。で、このスピーディな「変換力」「置換力」が記憶術では重要な能力になります。
実際のところ、記憶術を使いこなせるかどうかの別れ目は「変換力」「置換力」の高さと速さといっても過言ではありません。
変換・置換のやり方
変換力や置換力が必要となるケースは、上記でも説明しましたが、
- 文章(抽象的な物事)
- 専門用語・概念(難解な物事)
- 数字
において適用されることが多くなります。
変換力の事例1~文章
文章は抽象的・難解な物事になります。こうした抽象的な物事の場合は、いったん具体的で分かりやすい物事に置き換えます。
法律の条文や、何らかの説明文といった難解で複雑な文章がそうですね。
文章の場合は「言葉単位」に分解して、それらを具体的なかたちに置き換え、そうして連想結合法でによって記憶していきます。
では、ここで、実際に事例をあげて変換力の一例をご紹介しましょう。日本国憲法の前文の一部を変換してみます。
| 憲法前文 | 変換 |
| 日本国民は | 日本列島(日本)に人(国民)が立っている |
| 正当に | 拳(こぶし)を突き上げるポーズ |
| 選挙された | 選挙カーの上で演説している |
| 国会における | 国会で議論している様子 |
| 代表者を通じて | 演台の前で演説をしている代表者 |
日本国憲法の前文の一部だけになりますが、このように前文を別の具体的な何かに変換(置換)します。そうして変換(置換)した諸々を「連想結合法」で暗記していくようにします。
なお記憶術を使って文章を覚える方法は、こちらにもあります。いくつかのやり方がありますので、適宜使っていくのがおすすめです。
 場所法・記憶の宮殿で文章を暗記する秘密の方法
場所法・記憶の宮殿で文章を暗記する秘密の方法 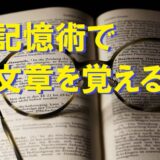 記憶術で文章・長文を覚えるやり方~憲法の前文を例に
記憶術で文章・長文を覚えるやり方~憲法の前文を例に  論文式試験専用記憶術ってどうなの?~購入者レビュー・ネタバレ・評価
論文式試験専用記憶術ってどうなの?~購入者レビュー・ネタバレ・評価
変換力の事例2~専門用語・概念
専門用語や概念の場合も、具体的でわかりやすい別の物事に変換・置換します。
ここでも事例をあげて説明してみましょう。事例となるのは、大学受験の日本史でもテーマになりやすい江戸時代の学問についてです。
馴染みのある言葉であれば、いちいち変換しないでそのまま使用することもできます。けれども江戸時代の儒学の用語に初めて触れた場合、次のような変換(置き換え)も可能になります。
◆江戸時代の学問を変換(置き換え)
- 儒学(孔子)・・・小牛がジュっと焼けて焼き土下座をしている
- 朱子学(朱熹:しゅき)・・・赤い種(種子)に文字(手記)が書いてある
- 陽明学(王陽明、孟子の性善説)・・・王様が酔っ払って(王酔う(陽命))、モー牛(孟子)と叫んでいる
- 古学(国学、朱子学を否定)・・・古典楽器の笙(しょう)(古学)で種子(朱子)を叩きつぶす
- 古文辞学(荻生徂徠)・・・おーギューっと絞られて(荻生徂徠)孤軍奮闘して痔になった(古文辞学)
これは、あくまで一例ですね^^;
こういう「ダジャレ」的な感覚で「変化(置き換え)」をすることもできるといった例になります。
こうした感じで、抽象的な言葉や難解な言葉をわかりやすい物事に置き換えていきます。
変換力の事例3~数字
数字の場合は「数字変換法」という記憶術もあります。また「語呂合わせ」もあります。けれども数字を何か具体的なものに置き換えて暗記するやり方もあります。
数字を暗記する場合は、あらかじめ「変換表(置換表)」を自分で作成しておいて、それに基づいて変換していきます。たとえば
- 0・・・霊柩車
- 1・・・イチゴ
- 2・・・ニンジン
- 3・・・サンダル
- 4・・・ヨット
- 5・・・ゴリラ
- 6・・・ロケット
- 7・・・七面鳥
- 8・・・ハチ
- 9・・・クジラ
といった感じです。これは一例ですが、自分の感性で使い勝手よく自由に作ることができます。
このようにあらかじめ数字と対応する変換表(置換表)を作っておいて、具体的な事物を置き換えて記憶をしていきます。
ちなみにこの方法は「ペグ法」になります。
 ペグ法記憶術(かけくぎ法)~数字(電話番号・歴史年号)の暗記に強い
ペグ法記憶術(かけくぎ法)~数字(電話番号・歴史年号)の暗記に強い
まとめ
以上の通りとなります。これらの具体例をみてもおわかりだと思いますが、「変換力」は記憶術にとっては重要な基本技術になります。
「変換」することができませんと、記憶術を使いこなすことはできないということもおわかりいただけたかと思います。
記憶術をマスターするには「変換力」が欠かせなくなります。